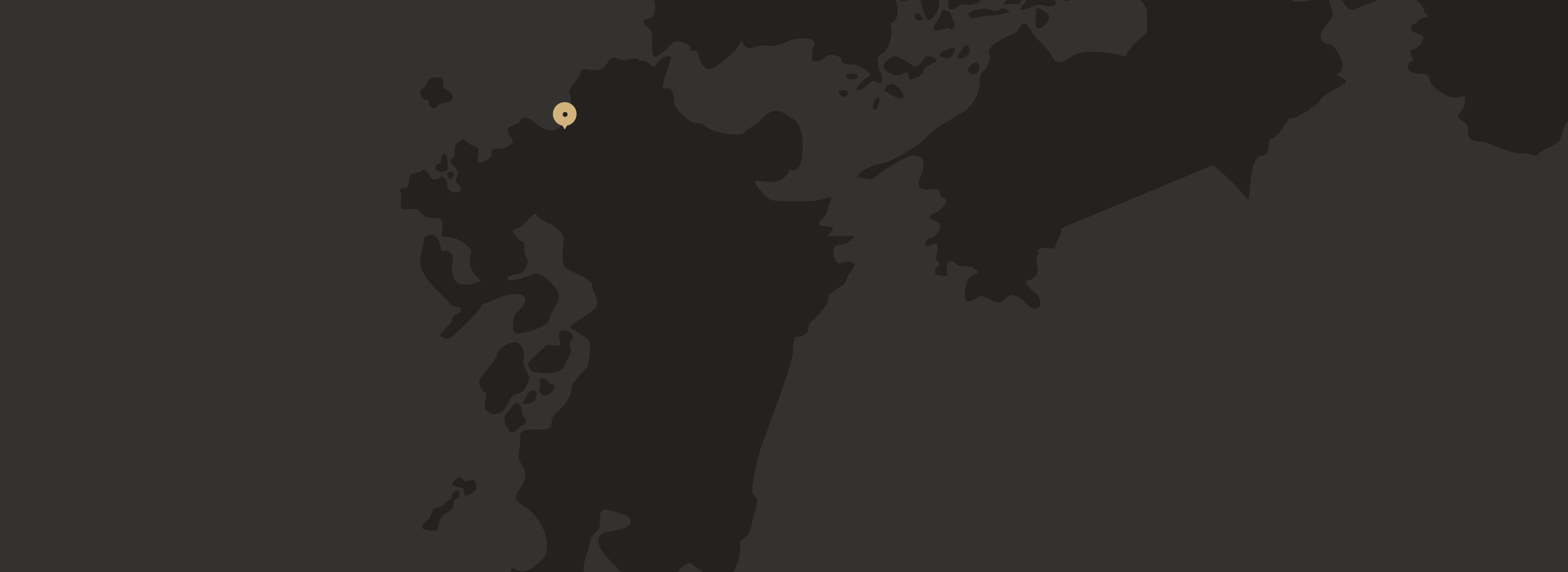Reservation空室検索・予約
航空券付きプラン
提携法人専用予約
2025.09.02
神さまがまちを歩く「放生会」 神職が語る千年の祈り
EVENTS

日本三大八幡宮のひとつである福岡の筥崎宮(はこざきぐう)。秋の訪れとともに、その参道にはたくさんの明かりが灯り、人々の笑顔が行き交います。放生会(ほうじょうや)の季節です。
博多三大祭りのひとつである放生会は9月12日から18日にかけて開催され、筥崎宮から続く道沿いには500店舗を超える露店が立ち並びます。
今やにぎやかなお祭りとして広く知られている放生会ですが、その起源は千年以上前にさかのぼります。
命を大切にする祈りの行事としてはじまったこのお祭りを支えているのが、筥崎宮の神職である飯田元矩(いいだもとのり)さん。
人と神をつなぐ役目として活躍される飯田さんだからこそ知る、華やかなまつりの裏にある真っすぐな想いについて紐解いていきましょう。
生命を慈しむことからはじまった放生会の祈り

境内で執り行われる鳩形(風船)の放生
京都の建仁寺に残る記録によると、放生会が生まれたのは西暦919年、平安時代のこと。 筥崎宮のご鎮座より4年も早く、祈りが捧げられていました。
神のお告げにより「万物の生命を慈しみ、秋の実りに感謝する神事」として始まった放生会の想いは、その後千年以上に渡って受け継がれていくこととなります。
「私たちの暮らしの中には、いただく命がたくさんあります。お米も、野菜も、魚も、肉も。 すべての命に感謝し、その尊さを思う。それが、このお祭りの原点です。」飯田さんは優しく教えてくださいました。

神職や子どもたちが稚魚を水辺に放つ放生の様子
期間中は動植物などの自然の恵みから食品生産を営む企業や料理店の供養祈願祭も催行されています。
また、放生会の最終日には神職や子どもたちが稚魚を境内の池に放つ放生神事が執り行われます。
参道のにぎわいとは違う、静かで清らかな時間。
命を思うやさしさこそ放生会の原点なのです。
露店が並ぶ参道で、まちと人の記憶がよみがえる

500店舗を超える露店と賑わう人々
日が暮れるころ、筥崎宮の参道前には多くの露店が 所狭しと並びます。どこか懐かしいお祭りの風景が、今も変わらず続いています。
「博多の人はお祭りが好きで、心のよりどころとなっていると思います。放生会も博多の祭りとして誇らしく思っていただけるとありがたいです。」と飯田さん。
“子どもの頃に行った”、“孫を連れて行くのが恒例行事”など、家族の思い出と結びついていることが多い放生会。毎年欠かさず訪れる方も多く、地域に愛されるお祭りなのです。
世代を超えて受け継がれるお祭りの記憶。例え景色が少しずつ変わっても、楽しくて温かい思い出は変わらず人々の心に残り続けます。

にぎわう参道を抜けた先には、神事や催しの舞台となる筥崎宮の境内が広がる
多くの人が楽しみに訪れる放生会。その魅力は、にぎやかな露店だけではありません。
「これほどの規模のお祭りはなかなかありません。境内ではさまざまな催しもありますし、神賑わい舞台では太鼓や神楽、演劇なども上演されます。伝統工芸に触れる機会もあるので、ぜひ多くの方に楽しんでいただけたらと思います」飯田さんは笑顔で語ります。
まちを巡る、神さまの旅

御神幸行列(ごしんこうぎょうれつ)の様子
放生会の期間中もっとも神聖な時間とされるのが、隔年で行われる御神幸行列(ごしんこうぎょうれつ)です。神さまが神輿(みこし)にお遷(うつ)りになり、まちを巡られる華やかな儀式で福岡市の無形民俗文化財に指定されています。
普段は筥崎宮のご本殿に鎮(しず)まる神さまが、宮司の付き添いのもとでまちへと出向かれます。離れの宮である頓宮(とんぐう)に泊まり、再び戻られる様子はまさに小旅行のよう。
昔は神輿を担ぎ船に乗せて運んでいたそうですが、現在は台車に乗せて陸路で移動します。

9月12日18時から執り行われる御発輦祭(ごはつれんさい)の様子
令和7年も例年通り、9月12日に「御下り(おくだり)」、14日に「御上り(おのぼり)」が予定されています。
12日の午前0時にご本殿の神様を神輿に移す儀式、同日夕方6時には鐘や太鼓が鳴り響く中で行列が執り行われます。14日の御上りでは、御下りと同じ道を逆に進み、筥崎宮へと戻るのです。
「前回の令和5年はコロナ禍を経て4年ぶりの開催だったので、準備も大変でした。前年の12月から動き出し、当日は4時間にわたる行列を安全に導くプレッシャーもあったんです。無事に終えたときは、本当に嬉しかったのを覚えています」
そう振り返る飯田さんの眼差しには、神職としての静かな誇りが宿っていました。

行列には白丁姿となった約500人もの人々が奉仕する
行列には、清道旗(せいどうき)や火王水王(かおうすいおう)、八ッ旗(やつはた)などの威儀物(いぎもの)を持った氏子たちが役割を担いながら随行します。
そして見どころのひとつが、御下りと御上りの終盤に氏子たちが最後の百数十メートルを駆け抜ける「駆け込み」。それぞれの道具を持ち力いっぱい走る迫力のある姿は、沿道の人々も思わず息をのむ光景です。
神職として祈りをつなぐこと

筥崎宮の神職 飯田元矩(いいだもとのり)さん
華やかな放生会の陰で、祭りを支えてきた飯田さん。神職として筥崎宮の広報担当を担いながら、 儀式の運営や地域との調整、安全面の配慮まで、放生会の舞台裏で多くの細やかな準備を重ねてきました。
「多くの人にとって、放生会は“楽しいお祭り”という印象だと思います。でもその根底には、命を思い、人を思い、まちを思う祈りがある。それを忘れずに守り続けるのが、私たち神職の役割だと感じています」

祝詞を読まれる神職
そして、神職の仕事には、神さまと人との間に立ち、祈りを捧げるという大切な役割があると言います。
神職は目には見えない想いや営みを、静かに未来へつなぐ存在でもあるのです。
「普段から筥崎宮には、さまざまな願いを抱えて多くの方が訪れます。その気持ちに真摯に向き合い、神職として神さまとの“橋渡し”の役目を果たしたいと考えています」
飯田さんの穏やかな口調には、祈りを預かる者としての誠実さが表れていました。
このまちに、祈りが灯り続けるように

放生会の最終日に執り行われる稚児行列で神職や巫女に先導される子どもたち
8年間にわたって放生会を見つめてきた飯田さんは、今年度末で筥崎宮での奉職を終え、地元の広島へ戻られます。
「この節目の年に、もう一度御神幸行列に関われるのは本当にありがたいことだと思っています。放生会は、時代とともに少しずつ形を変えてきましたが、“生命を慈しむ”という本質は、変わらずに受け継いでいきます」
にぎわいの中に、静かに宿る祈り。
その祈りは千年の時を超え、これからもこのまちに灯り続けます。
放生会(筥崎宮全域で開催)
日時:9月12日~18日
電話番号: 092-641-7431(筥崎宮社務所)
住所:福岡市東区箱崎1-22-1
アクセス:福岡市営地下鉄 箱崎宮前駅 より徒歩3分
HP: https://www.hakozakigu.or.jp/omatsuri/houjoya/
詳細は上記のリンク先でご確認ください。