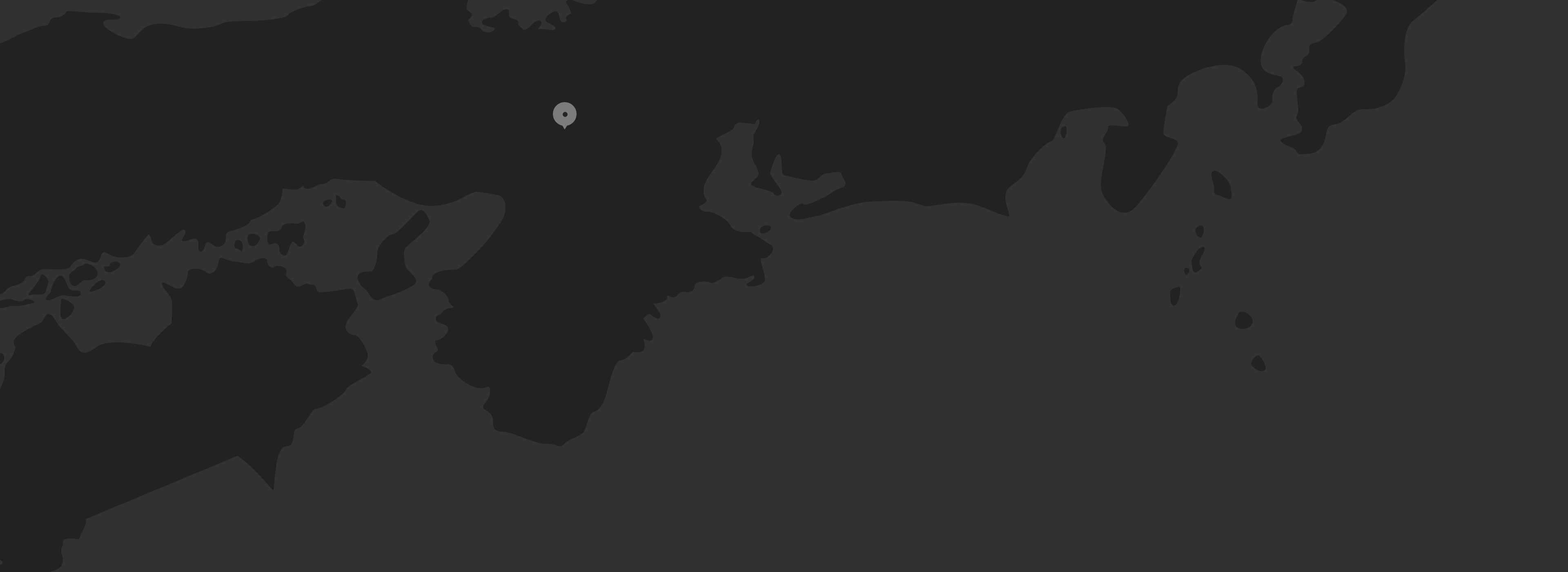Reservation空室検索・予約
航空券付きプラン
提携法人専用予約
2025.05.20
伝統と創造が交わる空間。京町家の雰囲気を味わえる「米澤工房」の陶芸体験

京都が誇る織物文化の中心地、西陣(にしじん)。ここには、間口が狭く奥行きが深い「うなぎの寝床」と呼ばれる京都伝統の木造建築、京町家が軒を連ねています。なかでも織り機を置くための吹き抜け空間を持つ「織屋建(おりやだて)」は、この地域ならではの特徴的な構造です。
そんな住宅が多く立ち並ぶ静かな路地に佇むのは、織屋建の伝統的な構造をそのまま活かした「米澤工房」。かつて西陣の職人たちが織物に魂を込めた場所には、陶芸の息吹が吹き込まれ、ろくろや手びねりといった手法による“京焼”の制作体験ができる空間へと生まれ変わっています。
職人の技と歴史が息づく工房空間

入口ののれんをくぐり、細い廊下を抜けた先に待つのは、外からは想像できないほどのひらけた空間。「高機(たかはた)」と呼ばれる背の高い織り機を置くために設計された吹き抜けの天井からは、自然光が降り注ぎ、工房となった作業スペースを明るく照らします。

「米澤工房」主宰の米澤猛さん
この空間で京焼の伝統を守りながら創作活動を続けているのが、米澤猛(よねざわ たけし)さん。祖父の代から京都・東山五条で工房を営んできた家系の3代目です。
知人から「陶芸のやり方を教えてほしい。」と頼まれたことがきっかけで、一般の人々に向けた陶芸体験を実施するようになった米澤さん。
京焼の制作は、地域の工房が1つの登り窯に作品を持ち寄る「共同焼成(しょうせい)」が主流でしたが、時代の移り変わりとともに各自が電気窯を持つようになったことで工房が手狭に。そうした背景もあり、25年前に西陣に場所を移すことになったそうです。
「京都らしい趣が感じられる織屋建の面構えが、体験に来るお客さまにも喜んでいただけるのではないかと思いここに決めました。」と、米澤さんは当時を振り返ります。
一つひとつ手作業で生まれる京焼の魅力

「米澤工房」の陶芸体験で制作できる作品見本
「京焼には、他地域の伝統的な焼き物のように、使う土や技法に決まったルールがないんです。」と、米澤さん。
焼き物の産地として有名な有田や瀬戸、信楽などと違い、京都では焼き物に適した”陶土(とうど)”がほとんど産出されません。
しかし長く都として栄えた京都では、貴族や茶人に献上する器づくりの需要が高まり、陶工たちは各地から陶土を集め様々な技術を取り入れながら、焼き物文化を発展させてきました。
そのため、京焼には多様な成形技法やデザインがあり、作家や窯元による個性が強く表れるのが特徴です。

モダンな雰囲気の米澤さんの作品「ZEBRA-POT(ゼブラポット)」
「最後は窯に委ねるところが、焼き物の面白さ。」と笑顔を見せる米澤さんは、窯から出てくるまでどのような姿に仕上がるかがわからない、その“予測不可能性”に魅力を感じるのだそう。
焼き物に色付けをするために塗る釉薬(ゆうやく)の色ムラや、手作業ならではの歪みが、焼成によって温かな風合いへと表情を変えていきます。
その京焼の奥深さを感じてもらうため、体験に参加するお客さまに、焼成前の写真を撮っておくことを勧めているそうです。
工房を貸切った陶芸体験で、特別な思い出を

電動ろくろを使った陶芸体験の様子
「米澤工房」の陶芸体験はグループごとに貸切で行われるため、織屋建の雰囲気を存分に味わいながら、家族や友人、カップルでプライベートな時間を過ごすことができるのも魅力の一つ。米澤さんは「体験を楽しんでもらって笑顔で帰っていただきたい。」という想いで、一人ひとりの作品づくりをサポートしています。
電動ろくろを使って器を成形していく体験は、“初心者でも職人気分を味わえる”と人気。手びねりでは、湯呑みやお皿はもちろん、置き物など幅広い作品を作ることができます。

「ハンコ皿」の制作体験の様子
また、小さな子どもでも参加できるように、型紙で形を作りハンコで好きな模様をつける「ハンコ皿」のコースもあり、家族連れにも好評なのだそう。成形後は、好みの釉薬を選んで色付けも可能。世界に一つだけのオリジナル作品に仕上がります。
作品は乾燥と焼成を経て約1ヶ月後に完成し自宅へ配送してもらうこともできるため、作品が到着するのを待つ時間も、旅の延長のようなワクワクした気持ちで過ごせそうです。
日常に旅の記憶が蘇る、自分だけの京焼

歴史を感じる京町家で、京焼という伝統文化に触れる贅沢なひととき。
かつて織機の音が響いていた空間に、今は土を捏(こ)ねる感触と自分だけの形を生み出す創造の時間が流れています。
自分で作った一点ものの焼き物で、お茶を飲んだり、食事を盛り付けたり、お気に入りの場所に飾ったり。
あなただけの物語が詰まった京焼作りは、旅の思い出が形となり日々の暮らしの中で何度も蘇る特別な体験となるはずです。
米澤工房
電話:075-467-3935
住所:京都市上京区御前通下長者町東入三助町280-4
アクセス:市バス(46)(201)「千本出水」バス停下車、徒歩8分
HP:https://www.y-kobo.net/
SNS:https://www.instagram.com/yonezawakobo_kyoto/
*営業時間や定休日についての詳細は、上記のリンク先にてご確認ください。